南米の心臓部で静かに鼓動する街
パラグアイという国名を口にしたとき、多くの人の頭に浮かぶのは漠然とした南米のイメージかもしれない。ブラジルとアルゼンチンという二つの大国に挟まれ、海を持たないこの内陸国は、しばしば「南米の心臓部」と呼ばれる。その心臓の鼓動を最も感じられる場所が、首都アスンシオンだ。
パラグアイ川のほとりに佇むこの街は、1537年にスペイン人によって築かれた南米でも最古の都市の一つである。コロニアル建築と現代的なビルが混在する街並みは、時の流れを物語る年輪のようだ。人口約50万人のこの街は、南米の大都市と比べれば小さく感じられるが、だからこそ人と人との距離が近く、温かな人情に触れることができる。
パラグアイの文化は、先住民グアラニーの伝統とスペイン植民地時代の影響が絶妙に混ざり合っている。公用語もスペイン語とグアラニー語の二つがあり、街を歩けばどちらの言葉も自然に耳に入ってくる。この二重言語文化は、パラグアイ人のアイデンティティの核を成している。
気候は亜熱帯性で、私が訪れる3月は夏の終わりから秋への移行期。まだ暑さが残るものの、夕暮れには心地よい風が頬を撫でていく。この季節のアスンシオンは、マンゴーやパパイヤが熟し、街角に甘い香りが漂う。
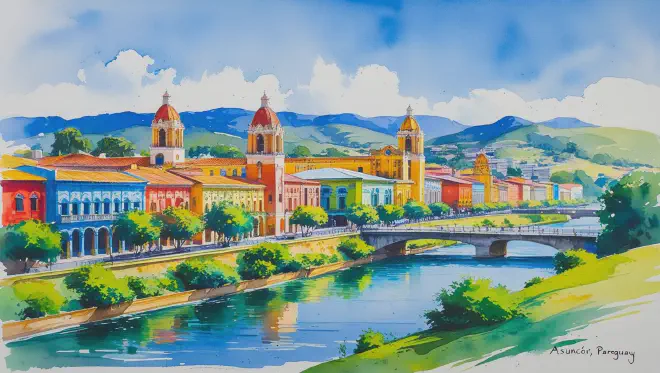
1日目: パラグアイ川に抱かれた古都への第一歩
シルビオ・ペティロッシ国際空港に降り立ったのは、午前10時過ぎのことだった。空港は決して大きくはないが、その分アットホームな雰囲気に包まれている。入国審査官の男性は、私の拙いスペイン語での挨拶に笑顔で応じてくれた。「¡Bienvenido a Paraguay! (パラグアイへようこそ!) 」その言葉に、旅への期待が一層高まった。
タクシーでアスンシオン市内へ向かう道中、窓の外に広がるのは赤土の大地と点在する低層の家々。運転手のカルロスさんは陽気な中年男性で、片言の英語と身振り手振りでパラグアイの魅力を熱心に語ってくれた。「アスンシオンは小さな街だが、心は大きいんだ」という彼の言葉が印象的だった。
午前11時半、市内中心部のホテルにチェックイン。コロニアル様式を現代風にアレンジした建物で、ロビーには地元アーティストの絵画が飾られている。部屋の窓からはパラグアイ川の流れが見え、対岸のランバレという町も望める。川面にキラキラと反射する陽光を眺めながら、長旅の疲れを癒した。
昼食は、ホテルから徒歩5分ほどの「ドン・ペドロ」という地元の人気レストランで。メニューを見ても何が何だかわからない中、ウェイトレスのマリアナさんが親切に説明してくれた。パラグアイの代表的な料理「ソパ・パラグアージャ」を注文。これはトウモロコシ粉とチーズで作った温かいスープのような料理で、初めて口にする味わいは素朴でありながら深みがあった。付け合わせの「チパ」というキャッサバ粉のパンも、もちもちとした食感が癖になる。
午後は、アスンシオンの歴史地区を散策した。まず向かったのは「プラサ・デ・アルマス」 (武器広場) 。この中央広場は1537年の建設当時から街の中心として機能してきた場所だ。広場の中央には、パラグアイの英雄フランシスコ・ソラノ・ロペスの銅像が立っている。周囲を囲むのは、大統領府 (パラシオ・デ・ロペス) 、国会議事堂、大聖堂といった重要な建物群。特に大統領府の白い外壁は、午後の陽射しに映えて美しかった。
大聖堂の中に足を踏み入れると、外の喧騒が嘘のように静寂に包まれた。薄暗い内部に差し込む色とりどりのステンドグラスの光が、神秘的な雰囲気を醸し出している。祈りを捧げる地元の人々の姿を見ていると、この街に根付く深い信仰心を感じることができた。
広場の周辺には露店が並び、手工芸品や民芸品が売られている。特に目を引いたのは「ニャンドゥティ」という伝統的なレース編み。蜘蛛の巣のような繊細な模様が美しく、作っている女性に話を聞くと、一枚完成させるのに数週間かかるという。その丁寧な手仕事に感動し、小さなコースターを購入した。
夕方になると、パラグアイ川沿いの遊歩道「コスタネラ」を歩いた。川幅は予想以上に広く、ゆったりとした流れが心を落ち着かせてくれる。釣りを楽しむ人々、ジョギングをする若者、ベンチで語り合うカップル。それぞれが思い思いの時間を過ごしている光景が、この街の穏やかな日常を物語っていた。
日が西に傾き始めると、川面が黄金色に染まった。対岸のランバレの街明かりがちらほらと点き始め、どこか郷愁を誘う風景が広がる。この瞬間、私は確かにアスンシオンという街の一部になったような気持ちになった。
夜は、地元の人に教えてもらった「ラ・カバーニャ」というステーキハウスへ。パラグアイは牧畜業が盛んで、牛肉の質は非常に高い。注文した「アサード」 (焼き肉) は、炭火でじっくり焼かれた牛肉が実に柔らかく、岩塩だけのシンプルな味付けが肉本来の旨味を引き立てていた。一緒にオーダーした「マンディオカ」 (キャッサバ芋) も、ほくほくとした食感で肉との相性が抜群だった。
食事をしながら隣のテーブルの家族連れと自然に会話が始まった。彼らは週末を祝って外食に来たとのことで、パラグアイ人の家族の絆の強さを垣間見ることができた。お父さんのルイスさんは建築業を営んでおり、明日は家族でイタウグアという陶芸の町に行くのだと教えてくれた。
ホテルに戻る途中、街の夜景を楽しんだ。アスンシオンの夜は決して華やかではないが、温かな街灯に照らされた街並みには独特の魅力がある。遠くから聞こえてくるギターの音色が、この初日を素晴らしく締めくくってくれた。
2日目: 伝統工芸の里と自然の恵みに触れる一日
朝6時、鳥のさえずりで目が覚めた。パラグアイの朝は早く、既に街には活気が戻り始めている。ホテルの朝食は、新鮮なフルーツとパン、そして地元のハーブティー「マテ茶」。マテ茶は南米全体で愛飲されているが、パラグアイのものは少し甘みがあって飲みやすい。現地の人は朝から晩まで、家族や友人とマテ茶を回し飲みしながらコミュニケーションを深めるのだという。
午前8時、昨夜出会ったルイスさん一家との偶然の再会から始まった一日。ホテルのロビーで彼らと鉢合わせし、「一緒にイタウグアに行かないか」と誘ってもらった。せっかくの機会なので、彼らの車に同乗させてもらうことにした。
アスンシオンから約30キロ、車で40分ほどの道のりをルイスさんの家族と過ごすのは、思いがけない贈り物だった。12歳の息子マルコスくんは英語を勉強中で、一生懸命に質問してくる。「日本にもサッカーチームはありますか?」「寿司は本当に生の魚なんですか?」その純粋な好奇心に、こちらも楽しく答えた。
イタウグアは「陶芸の街」として知られる小さな町だ。到着すると、赤茶けた土と青い空のコントラストが美しい。町の至る所に陶芸工房があり、職人たちが黙々と作品作りに取り組んでいる。私たちが訪れたのは、50年以上続く老舗工房「アルファレリア・トラディシオナル」。
工房の主人、ドン・エミリオさんは70歳を超える熟練の陶芸家だった。彼の手にかかると、ただの粘土が見る見るうちに美しい壺や皿に変化していく。「土と対話することが大切なんだ」という彼の言葉は、まさに職人の哲学を表していた。私も体験させてもらったが、なかなか思うようにはいかない。それでも、土の感触を通じて何か原始的な創造の喜びを感じることができた。
工房の中庭で、ドン・エミリオの奥さんが作ってくれた昼食をいただいた。「ロクロ」という伝統的な煮込み料理で、豆類と野菜、少しの肉が入った素朴で滋養豊かな味わい。一緒に出された「エンパナーダ」 (具入りのパイ) も、手作りの温かさが伝わってくる。
食事の後、ルイス一家と別れを告げ、午後はアスンシオンに戻って植物園を訪れた。「ハルディン・ボタニコ・イ・ソオロヒコ」は市内からバスで20分ほどの場所にある。ここは植物園であると同時に動物園でもあり、パラグアイの豊かな自然を一度に体験できる貴重な場所だ。
園内に入ると、まず驚かされるのは巨大なセイバの木だ。樹齢数百年というこの木は、まさに自然の威厳を体現している。その周囲には、パラグアイ固有の植物が数多く植えられており、係員の女性が丁寧に説明してくれた。特に印象的だったのは「ヤカランダ」の木。紫色の美しい花を咲かせるこの木は、パラグアイの国花でもある。
動物園エリアでは、南米特有の動物たちと出会った。アルマジロ、カピバラ、そして色鮮やかなオウムたち。中でも「ヤグアルンディ」という小型のヤマネコは、警戒心が強く普段は姿を見せないのだが、この日は運良く日向ぼっこをしている姿を見ることができた。その野性的でありながらも愛らしい表情に、しばらく見とれてしまった。
夕方、植物園から市内へ戻る途中、バスから見える夕景が素晴らしかった。パラグアイの大地を染める夕陽は、どこまでも広い空の下で特別な美しさを放っている。バスの中で隣に座った老婦人が、「私たちの国は小さいけれど、空だけは世界一大きいのよ」と微笑んで話しかけてくれた。その言葉に、パラグアイ人の誇りと愛国心を感じた。
夜は、マルカル地区にある民族音楽のライブハウス「ペーニャ・フォルクロリカ」を訪れた。週末の夜ということもあり、地元の人々で賑わっている。ステージでは、ギターとアルパ (パラグアイ固有のハープ) による演奏が行われていた。特にアルパの音色は繊細で美しく、心の奥深くに響いてくる。
演奏されたのは「グアラニア」というパラグアイの伝統音楽。スペイン語とグアラニー語が混じった歌詞は、恋や故郷への思いを歌ったものが多い。言葉は完全には理解できなくても、メロディーと歌手の表情から伝わってくる感情は普遍的で、思わず涙ぐんでしまった。
観客の中には、一緒に歌を口ずさむ人も多い。その光景を見ていると、音楽が人々の心を繋ぐ力を改めて実感した。休憩時間には、隣のテーブルの若いカップルが私に話しかけてくれ、パラグアイの音楽について熱心に教えてくれた。彼らの音楽に対する愛と誇りは、聞いているこちらも温かい気持ちにしてくれた。
ホテルに戻る夜道、頭の中にはまだアルパの美しい音色が響いていた。この日一日で、パラグアイの伝統文化の深さと、それを大切に受け継ぐ人々の心の豊かさに触れることができた。それは旅の大きな収穫だった。
3日目: 別れの朝と心に残る風景
最終日の朝は、いつもより早く目が覚めた。おそらく、この街との別れが近づいていることを心のどこかで感じ取っていたのだろう。窓の外を見ると、パラグアイ川にうっすらと朝霧がかかっている。幻想的な光景に、しばらく見とれてしまった。
荷造りを済ませ、チェックアウト前に最後の朝食を楽しんだ。いつものマテ茶がこの日は特別な味わいに感じられる。ホテルのスタッフたちも、「また戻ってきてください」と温かく声をかけてくれた。短い滞在でも、彼らとの間に築かれた小さな絆を実感した。
午前中は、まだ訪れていなかった「メルカード4」という市場を探索することにした。ここはアスンシオン最大の市場で、食材から日用品、衣類まで何でも揃う庶民の台所だ。朝の8時だというのに、既に多くの買い物客で賑わっている。
市場の中は迷路のように複雑で、様々な匂いと音が混じり合っている。野菜売り場では、見たことのない南米特有の野菜が山積みになっている。果物売り場では、マンゴー、パパイヤ、パッションフルーツなどが色鮮やかに並んでいる。試食させてもらったマンゴーは、これまで食べたどのマンゴーよりも甘くて濃厚だった。
肉売り場では、巨大な牛肉の塊が吊るされており、注文に応じてその場で切り分けてくれる。魚売り場には、パラグアイ川で獲れた川魚が並んでいる。中でも「スルビ」という大型の川魚は、パラグアイ料理には欠かせない食材だという。
市場の一角で、おばあさんが作る「ソパ・パラグアージャ」の屋台を見つけた。初日に食べた味を懐かしく思い出し、もう一度注文してみた。やはり温かくて優しい味わいで、旅の疲れを癒してくれる。おばあさんは私が外国人だと分かると、「パラグアイはどうだった?」と聞いてくれた。「素晴らしい国です」と答えると、深い皺に囲まれた彼女の目が嬉しそうに輝いた。
市場を後にして、最後にもう一度コスタネラを歩いた。昨日とは違い、平日の午前中ということもあって人は少ない。パラグアイ川は相変わらずゆったりと流れ、対岸の景色も穏やかだ。ベンチに座って、この3日間を振り返った。
出会った人々の顔が次々と浮かんでくる。タクシー運転手のカルロスさん、レストランのマリアナさん、イタウグアのドン・エミリオさん、ルイス一家、植物園の係員、バスで隣に座った老婦人、音楽を教えてくれた若いカップル、市場のおばあさん。みんな、私を温かく迎え入れてくれた。
パラグアイという国は、確かに小さく、世界的にはそれほど知られていない。しかし、その分だけ人と人との距離が近く、旅行者でも家族の一員のように扱ってくれる温かさがある。経済的には決して豊かではないかもしれないが、心の豊かさという点では、どこの国にも負けないものを持っている。
午後1時、空港へ向かうタクシーを呼んだ。運転手は行きとは違う人だったが、やはり陽気で親切な中年男性だった。「パラグアイを気に入ってくれたかい?」という質問に、私は心から「はい、大好きになりました」と答えた。
空港に着くと、まだ時間があったので、土産物店で最後の買い物をした。ニャンドゥティのテーブルクロス、イタウグアの陶器、そしてパラグアイ産のハチミツを購入。どれも、この旅の思い出を形にしたものだった。
搭乗手続きを済ませ、待合室でアスンシオンの街を見下ろした。小さな街だが、この3日間で私の心に大きな印象を残してくれた。きっと、これからも折に触れてこの街のことを思い出すだろう。
飛行機が離陸すると、眼下にパラグアイの大地が広がった。赤い土と緑の草原、そしてゆったりと流れるパラグアイ川。上空から見ても、この国の穏やかさと美しさは変わらない。窓にもたれながら、私は心の中で「ありがとう、パラグアイ」と呟いた。
空想でありながら確かに感じられたこと
この旅は空想でありながら、私の心の中では確かにあったもののように感じられる。アスンシオンの街並み、パラグアイ川の流れ、出会った人々の笑顔、伝統音楽の美しい響き、素朴で温かい料理の味—それらすべてが、今でも鮮明に記憶に残っている。
パラグアイという国は、世界地図の中では小さな存在かもしれない。しかし、そこに暮らす人々の心の温かさ、受け継がれてきた文化の豊かさ、そして自然の美しさは、決して小さなものではない。むしろ、現代社会が忘れがちな大切なものを、この国は大切に守り続けているように思える。
旅とは、新しい場所を訪れることだけではない。新しい出会いを通じて、自分自身を見つめ直すことでもある。この空想の旅を通じて、私は改めて人と人との繋がりの大切さ、文化を尊重することの意味、そして心の豊かさとは何かということを考えさせられた。
パラグアイの人々が教えてくれた「心の大きさ」は、きっと実際に旅をしても感じることのできる、この国の真の魅力なのだろう。いつか本当にこの地を訪れる日が来たら、今回の空想の旅で出会った人々のような温かい笑顔に迎えられることを、心から願っている。

